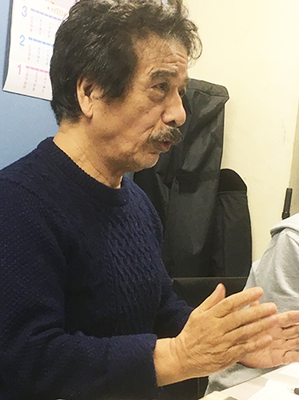『この世界の片隅に』とフォーク黎明期の共通点
牧村:僕も悠さんにいろいろ聞きたいんだけど、悠さんが起業して烏山ロフトをオープンさせた時はジャズをメインにかけていたんですよね。
平野:そう、レコードがたかだか100枚くらいしかないジャズ喫茶。すごいでしょ?(笑)
牧村:烏山ロフトでライブをやる発想はなかったんですか。
平野:当時は考えもしなかった。ただ、若者文化の時代だったから千歳高校や新宿高校とか若い連中の集まりは大事にしたし、まだ若かった坂本龍一やノンフィクション作家の生江有二、ジャーナリストの二木啓孝といった気鋭の論客も常連だったんだよ。
牧村:このあいだ坂本さんと会った時に言ってましたよ。「烏山ロフトにはホントによく通ったんだよ」って。
平野:坂本さんはもともとクラシックの世界でピアノを弾いてた人だから、ロフトがなければ彼はロックに行かなかったんじゃないかな。多分ね。烏山を始め、西荻、荻窪、下北沢、新宿と全部のロフトに坂本さんは顔を出してたし、フォークやロックの人脈とはほとんどウチで知り合ってるんだから。
牧村:悠さんがフォークやロックに目覚めたのは、その烏山ロフトの時代ですよね。
平野:そうだね。あまりにレコードが少なすぎるということで、お客さんがレコードを持ってきてくれるようになったんだよ。ジャズに限らず、浅川マキとか友部正人とかさ。そのなかにあったはっぴいえんどにぶっ飛んだわけ。彼らが日本語で唄うロックは詩的だし、圧倒的な質の高さがあった。そうやって日本のロックを面白く感じるようになると、烏山ロフトはもはや純粋なジャズ喫茶ではなく、フォークやロック、ジャズもかける雑多な店になった。最終的には歌謡曲や浪曲までかけてたからね(笑)。
牧村:烏山ロフトのオープンは71年。当時は世の中自体がすごく面白くて、もう一度ああいう面白い時代が来る気配はいまのところないですが。だけど、こういうことは言えます。いまみたいに面白くない時代ほど面白い表現が生まれる。
平野:なるほど、それは言えるかもしれない。
牧村:アメリカでトランプが大統領になって失望してる人も多いけど、彼はマイナスのクリエイターなんです。トランプが大統領になることで数々のとんでもないことが起こるだろうけど、そんなことは許さない! という人が少数であっても、1割くらいは出てくるはず。そうなると面白いことが始まるのです。それは日本も同じで、どうしようもない党や指導者の支持率が60%を超えて、それに対抗できるだけの人材もいない。でも、そういう時に限って何か新しいものが芽生えるんです。最初はマイノリティだけど。不思議なもので、いい時代にいいものは芽生えないんですよ。
平野:こんな時代だからこそ生まれる面白い表現とは、具体的に言うとどんなものだろう?
牧村:たとえば、片渕須直監督のアニメーション映画『この世界の片隅に』。興味を持つきっかけがいくつかあったんですよ。一つは加藤和彦さんが作曲した「悲しくてやりきれない」が主題歌扱いだったこと。加藤さんと僕は一時期、行動を共にしたし、生きていればこうしてあなたの曲が愛され続けているのを知れたのに…という思いがあった。もう一つは、「悲しくてやりきれない」をカバーして、映画音楽を担当したコトリさんが素晴らしかったこと。最初、この映画は10年くらいかけないと出資金を回収できないという話を聞いていたんだけど、これは興行収入10億円を達成させなくてはいけない映画だと試写を見て思った。それで勝手に宣伝の手伝いをやりたくなったんです。
平野:牧村さんの見立て通り、興行収入が10億円を突破したんだってね。劇場も封切り時は50館ほどだったのが200館を超えるそうで。
牧村:さっきの話しに戻りますが、世の中がどれだけ悪くなっても1割くらいの人には打てば響くんですよ。だったら打てばいい。お金がなくてもネットがあるし、そこに自分の意見を書き綴ればいい。そうすると同じ思いの人が見えてきたし、集まってきた。そういう人たちと生涯会うことはないかもしれないけど、仲間ですね。僕としては、同じ人が10回映画を観るよりも、10人に映画を観て欲しかったんです。そのうちゴスペラーズの黒沢薫さんやゴールデンボンバーの歌広場淳さんたちが、既に映画を広めていたことを発見したんです。そうやってあちこちで輪が広がっていった。
平野:それは素晴らしいね。主演ののんちゃんが芸能界を干されて、この映画の監督が彼女を抜擢したんだよね。そういう背景もあって、これは何とかしなきゃいけないって気持ちもあったんでしょう?
牧村:聞くところによると、のんさんの起用は当初反対意見があったようです。おそらく、プロモーションが思うようにできないよ、って。でも片渕監督は作品のクオリティ優先で、いい作品を作りたい一心だったそうです。その状況は僕が70年代にやっていたこととそっくりなんですよ。
平野:メジャーから全く相手にされない、テレビやラジオも味方してくれない、それでもインディーで地道にやれることはあると。その精神がいまも生き続けているわけだ。
牧村:そういうことですね。たとえばはっぴいえんどのレコードはいまだに何度も再発されてロングセラーを記録してるけど、オリジナルが出た時は、よくて2,000枚程度の売り上げだった。でも、いいものであれば自ずと広がっていくものなんですね。八方塞がりの時代でもいい作品は支持されるし、作った作品や動機に対して協力してくれる人たちが少なからずいる。その人たちが一丸となって前へ進めば必ず道は開ける。それは僕らが70年代にやっていたことと同じですよ。『この世界の片隅に』は興行収入が10億を超えて、20億、30億を目指せ! という声が聞こえ始めた時点で、僕の勝手な応援は終了しました。ここからはその道のプロの仕事ですから。悠さん、年を取った僕らにできるのは「このやり方はうまくいったよ」とか「これは信じてもいいんだよ」という自分の経験で得たものを伝えることなんです。あまり多くはないけれど、僕は自分なりのノウハウを残しておきたい。残せる財産がない代わりにね。なんて言うのかな、いまの時代、みんな暗く下を向いてばかりでしょう。そんなに絶望する必要はないよ、って言いたいんですよ。そんな人間がいたっていいじゃないですか。

あらゆる音楽はポップスになるということ
平野:弱小のインディーズ映画だって、やり方次第で大ヒットするんだからね。でも面白いね、牧村さんはビッグ・ビジネスになりかけた瞬間にサッと身を引いちゃうんだから。
牧村:ビッグ・ビジネスになるとある意味腐敗するんですよ。僕らもかつては淵にいたのに、真ん中へ行って成功した途端に腐敗してしまったから。
平野:そこが牧村さんと僕の違いかな。腐敗するほど成功してないからね(笑)。僕はニューミュージックの全盛時に、こんな軟弱な連中に自分たちの支持する音楽を任せられるか! と思ったの。ここが重要で、儲かる音楽じゃなくて支持する音楽が大事なんだよ。それで僕はパンクへ移行するわけ。だけど牧村さんたちはパンクについてこれなかったでしょう?
牧村:パンクが出てきた78、9年の頃はサザンや竹内まりや、YMOがデビューして、その後、70年代に切磋琢磨してきた人たちに光が当たり始めるんですね。僕らが携わったミュージシャンたちが本当の意味で脚光を浴びたのは82、3年頃なんですよ。当時の僕らは最後の、言わば完成形を作っていた段階だったんです。悠さんはパンクという新しい時代の音楽に着手していたけど、僕らは手がけてきたものを完成させなくちゃいけなかった。未完成のまま放り出してしまったらそれまでの10年が無駄になってしまう、自分たちが始めたことの起承転結をちゃんとしたかった。ただし、覚悟はしましたよ。起承転結の「結」が来るということは、成功と共に片側ではゼロになるってことだから。
平野:そう、問題はそこだよな。僕らは店をやってるからゼロになるわけにはいかないんだよ(笑)。
牧村:1985年にニッポン放送の亀渕昭信さんが音頭を取って、国立霞ヶ丘陸上競技場で『国際青年年記念 ALL TOGETHER NOW』という大規模なジョイント・コンサートが開催されたんですよ。それに出たのが再結成したはっぴいえんど、松任谷由実さんや坂本龍一さんが参加したサディスティック・ユーミン・バンド、拓郎さん、オフコース、佐野元春さん、サザンといった豪華な面子でね。でも、コンサートが終わった後の打ち上げで、大瀧さんが若い音楽家に言ったんです。「今日はニューミュージックの葬式だったんだよ」ってね。少なくても当時の大瀧さんは、あのライブではっぴいえんどを完全に終わらせたということなんでしょう。僕も、そのライブで70年代にやってきたことはすべて終えた思いがありましたね。68、9年に出口が見つからずにやむを得ず選んだ音楽の道が、16、7年を経て一巡りして終わったわけです。実際、僕はそこで音楽制作の仕事を一度やめました。それが一つの宿命だと思うんですね。
平野::なるほど、決してパンクについていけなかったわけじゃないんだね(笑)。
牧村:日本語のフォークやロックを生み出した時代の一員としては、それと共に終焉を迎えるしかなかったんです。途中でパンクに乗り換えていたら、それはもうビジネスマンですよ。自分で選んだ扉は一つしかなかったし、その扉が閉まる時は共同体なんだから。
平野:もし牧村さんみたいなスペシャリストがパンクに関わっていたら、あの時代のパンクの動きももう少し違ったものになったんじゃないかと僕は思うわけ。パンク出身で一番の成功例はBOOWYだと思うけど、成功すれば何のメッセージ性もないポップなパンクで終わっちゃうじゃない? そこが僕には腑に落ちないところがある。
牧村:そういう話を聞いて思い出すのは、音楽評論家の相倉久人さんの言葉ですね。対談してもらった本のなかで相倉さんが僕に何度も言っていたのは、「あらゆる音楽はポップになる」ということ。ジャンルに関係なく、それが流行った時点で、売れた時点でポップスになるんですよ。それが売れたものの宿命なんですね。